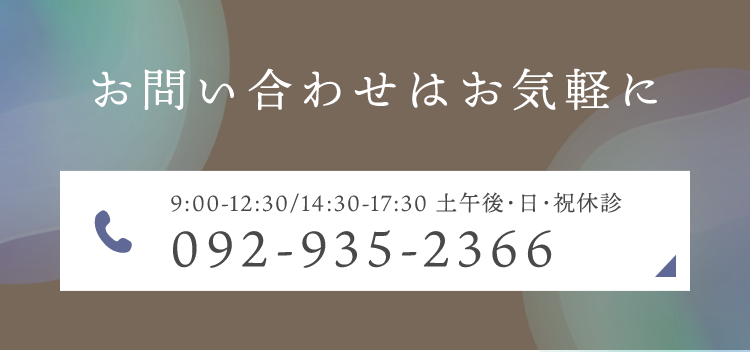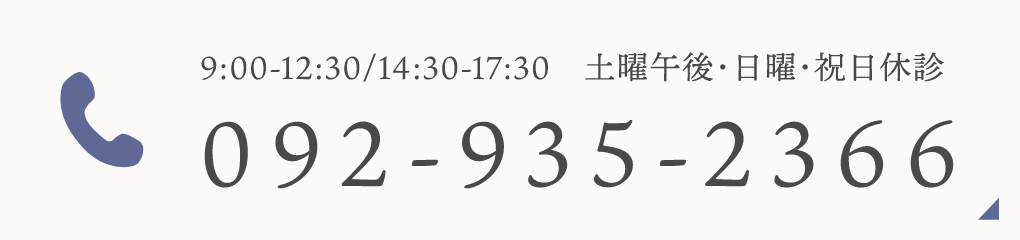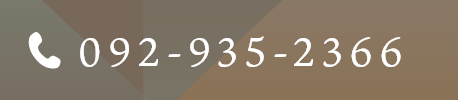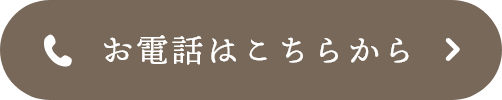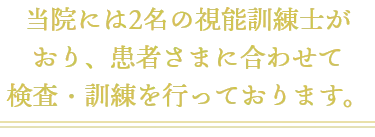
当院には2名の視能訓練士がおり、患者さまに合わせて検査・訓練を行なっております。
弱視
弱視とは?
メガネやコンタクトレンズで矯正しても視力があがらないことをいいます。裸眼視力が0.1以下でも、メガネやコンタクトレンズで矯正して1.0以上の最大矯正視力があれば「弱視」ではありません。
治療方法
基本的にはメガネ装用です。メガネで矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り、視機能の発達を促すことが必要です。 当院では適正な検査を行い、その上で弱視訓練なども行なっております。視力が発育するまでは定期的に通院検査を行い、回復するまでのサポートをしております。 何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
治療方法
基本的にはメガネ装用です。メガネで矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り、視機能の発達を促すことが必要です。
当院では適正な検査を行い、その上で弱視訓練なども行なっております。視力が発育するまでは定期的に通院検査を行い、回復するまでのサポートをしております。
何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
斜視
斜視とは?
片方の目が見ようとするものを見ていても、もう片方の目が内側や外側、あるいは上下に向いていることをいいます。斜視は子供の2%くらいにみられる病気です。
治療方法
手術により、目を動かす筋肉(外眼筋)の付いている位置をずらすことで、眼の位置を改善します。
成人の場合、局所麻酔で日帰り手術ができます。乳幼児や学童期以下の場合は、全身麻酔で手術をおこないます。
手術以外にも治療法はあり、コンタクトレンズやメガネを装用することで、斜視の原因となっている遠視や近視を矯正し、両眼で正常に見えるようにして両眼視をさせる方法も有効的です。
当院では斜視視能訓練を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
治療方法
手術により、目を動かす筋肉(外眼筋)の付いている位置をずらすことで、眼の位置を改善します。
成人の場合、局所麻酔で日帰り手術ができます。 乳幼児や学童期以下の場合は、全身麻酔で手術をおこないます。
手術以外にも治療法はあり、コンタクトレンズやメガネを装用することで、斜視の原因となっている遠視や近視を矯正し、両眼で正常に見えるようにして両眼視をさせる方法も有効的です。
当院では斜視視能訓練を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
色覚異常
色覚異常とは?
正常とされる他の大勢の人とは色が異なって見えたり感じたりする状態のことをいいます。色の区別がつきにくい場合があり、日常生活に支障をきたしてしまう可能性があります。
色覚異常には先天性と後天性があり、先天性では日本人男性の20人に1人(5%)、日本人女性の500人に1人(0.2%)といわれています。後天性では加齢による色覚異常は水晶体(目のレンズ)が年とともに黄色く変色すること(白内障)や、瞳が小さくなり目に光が入りづらくなること、網膜の視神経の劣化など複合的な要因によって起こります。
はやり目
はやり目とは?
感染力が非常に強く、主に手を介して伝染します。目やにが多くでたり、充血したりしますが、症状が重い場合は黒目(角膜)に傷がつき、傷跡が残る角膜混濁になったり、まぶたの裏側に炎症の白い膜(偽膜)ができることがあります。
治療方法
アデノウイルスに対する薬剤ではありませんが、他の細菌などの混合感染を防ぐために抗菌薬の点眼を行います。
角膜の濁りがみられる場合は、ステロイド薬の点眼を行います。
治療方法
アデノウイルスに対する薬剤ではありませんが、他の細菌などの混合感染を防ぐために抗菌薬の点眼を行います。
角膜の濁りがみられる場合は、ステロイド薬の点眼を行います。
学校健診で眼科受診をすすめられた方
視力検査の結果
現在、学校での視力検査の結果はA・B・C・Dの4段階による判定です。A(1.0以上):教室の一番後ろでも黒板の字が問題なく見える。
B(0.7〜0.9):教室より真ん中より後ろの席だと、黒板の小さい字が見にくいことがある。
C(0.4〜0.6):教室の真ん中より前の席でも、黒板の小さい文字が見にくい。
D(0.3以下):教室の一番前の席でも見にくい。
この4段階判定は370(さんななまる)方式といい、学校で検査する視力の方法です。0.3・0.7・1.0の3種類の大きさの視力表を使って視力を検査します。そのため、眼科で検査する視力の方法とは違います。眼科では、より細かくお子さまの様子を見ながら視力検査をします。
裸眼視力・矯正視力(メガネ上・コンタクト上)の結果がA以外の場合、学校から用紙が配布されますので用紙を持参のうえ、早めにご来院いただければ詳細の視力検査を行います。メガネ・コンタクトをお持ちの方は、一緒に持参してください。
実際にはよく見えているけれど、上手に検査が出来なかったため結果がよくなかったケースもあります。
遠視・近視・乱視の屈折異常によって視力が出にくい場合は、眼科での検査・診察結果で、お子さまにあった治療方法の選択、生活指導を行います。特に遠視や乱視の場合は弱視と言って、将来の視力に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。この場合は、早急に対応しないと手遅れになるケースもあるため注意が必要です。
お子さまが見えにくいと訴えていなくても用紙をもらった場合は必ず受診するようにしましょう。
現代では、スマートフォン・タブレット・ゲーム機などの急速な普及により、手が届くところに娯楽や情報を知ることができます。お子さまの中には、遠くが見にくいことをあまり実感していないことがあります。近くのものが見えて楽しめていれば見えていると言ってしまうことも少なくありません。そのため眼科では、学校生活・日常生活で遠くを見るときに困っていないか、見にくいのを我慢していないかをお子さまとの会話や視力検査で確認していきます。
メガネの作成を希望される場合でも、お子さまの眼の状態によって詳しい検査を必要と判断した場合は、別の日にメガネの作成になる場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。
その他、お子さまの眼に関する気になることがあればお気軽にご相談ください。